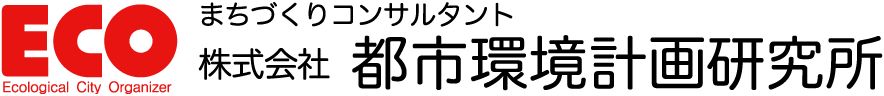STUDY研究活動・社会貢献
摂田屋まちあるき
(M.M.)
はじめに
今回の研修で初めての訪問となった長岡市。長岡と言えば、「いつか花火大会に行ってみたいなあ」などと思っていたくらいで、「発酵・醸造のまち」とは全く認識していなかった。酒蔵も市内に16蔵あるらしく、京都市に次ぐ全国第2位の多さだ。中でも摂田屋地区は、古くから酒・味噌・醤油などの醸造が盛んな町として、歴史ある建物や町並みも大切にしている地区である。
歴史のまち 摂田屋
江戸時代に交通の要所として栄えた摂田屋。そんな摂田屋の語源は“接待屋(せったいや)”だそう。街道を行く人のための無料休憩所があり、それに由来すると言われている。摂田屋は太平洋戦争からも危うく難を逃れ、明治期から残る趣ある建築物も多数残っている。また、平成16年の中越地震では各蔵元の建物に被害が出たが、それがきっかけとなり、地区に残る歴史的な建造物をはじめとする景観の保護保存活動を始めるべく、NPO法人「醸造の町摂田屋町おこしの会」が設立され、地域の人が協力して復興に力を注いだ。摂田屋は、10年ほど前から積極的に観光客を受け入れるようになり、観光客が訪れることで地域の人たちも町の歴史に対する考え方が変わるようになったそうだ。
まちあるきの記録
実際に地区内を歩いていると、醤油のような香りがほんのり漂ってきた。まず訪れたのは、旧機那サフラン酒本舗。敷地内に現存する歴史的建造物の全てが国の登録有形文化財となっている。長岡市は平成29年から保存整備計画をスタートし、第1弾として、令和2年に米蔵を改装した「摂田屋6番街 発酵ミュージアム・米蔵」がオープンした。今後、約10年をかけて残りの9つの建物や庭園も整備していくようだ。
 ▲旧機那サフラン酒本舗
▲旧機那サフラン酒本舗
続いて長谷川酒造。天保13年創業で昔ながらの手作業にこだわり酒造りを行っている。長谷川酒造は、初代の重吉が酒造りの許可を受けたことに始まるとされる。今回は外観を見学したのみだったが、また訪れた際には、主屋の1階で販売されているお酒もじっくり見てみたい。
 ▲長谷川酒造
▲長谷川酒造
続いて越のむらさき。天保2年創業の醤油醸造会社で、レンガ造りの煙突が町のシンボルにもなっている。平成16年の中越地震では、蔵の壁にひびが入り、レンガの煙突が損壊するなどの被害を受けたが、町の人と話し合い、修復して残すことになったそうだ。それが今もなお、町の財産として残っている。
 ▲越のむらさき
▲越のむらさき
続いて、休憩がてら江口だんごでお団子をいただいた。こちらは、かつて越のむらさきの創業家の邸宅だった場所に令和4年にオープンした。敷地内には地下1階、地上2階建ての蔵もあった。昭和5年に建築された蔵をリノベーションし、LOCAL IDENTITY STORE「LIS」が新たに入ったそうだ。1階では醸造リキュール等の販売、2階はギャラリー展示や本の販売をしていた。お土産にぴったりな日本酒ガチャというものもあり、ついつい手が伸びてしまった。
 ▲江口だんご
▲江口だんご
そして最後は、令和2年にオープンした、旧機那サフラン酒本舗の保存整備計画第1弾として改装された摂田屋6番街 発酵ミュージアム・米蔵を訪れた。天井が吹き抜けになっており、ゆったりとした時間が流れていた。地元食材を活かしたメニューを堪能できるカフェや、「発酵」について楽しく学べるラボ、長岡出身の絵本作家・松岡達英さんの絵本コーナーなど、大人も子ども楽しめるような場所になっていた。
 ▲摂田屋6番街 発酵ミュージアム・米蔵
▲摂田屋6番街 発酵ミュージアム・米蔵
そのような新しい施設としての整備も進む一方、観光地化することが目的とはならない。歴史と活用のバランスが問われるなと感じたまちあるきだったが、これからそのような観光地としての場が新たに整備されるのは非常に楽しみである。
さいごに
恥ずかしながらも、今回の研修で摂田屋という町を初めて知ったが、日本酒好きにはたまらない町だった。それだけではなく、歴史的な趣のある建物が数多く残る中、それらを改装した新たな施設などもあり、非常に楽しいまちあるきだった。また旧機那サフラン酒本舗の建物や庭園が整備されたときには是非足を運びたいと思う。